「ボーロ(ぼうろ)」の由来とおすすめのテイクアウト容器のご紹介

こんにちは、業務用テイクアウト容器通販サイト「折箱堂」スタッフの佐藤です。
赤ちゃんの離乳食、こどものオヤツから大人まで幅広い世代に愛される「ボーロ」。
我が家でも、息子たちが小さい頃は「たまごボーロ」にお世話になりました。
小さくて丸くて、口に入れるとすぐ溶けるので安心ですね。又、歯が腫れてものが噛めないとき、「たまごボーロ」や「そばぼうろ」を口の中で溶かしながらよく頂きます。
ホント年を取っても重宝いたします。お土産に頂いた「丸ぼうろ」は、ふんわり感が心地よく柔らかい甘さで食が進みます。
日本では昔から愛されている和菓子の一つである「ボーロ(ぼうろ)」ですが、なぜ「ボーロ」と呼ばれているのか、いつ頃から登場したのか、実はわたしもこの記事を書くまであまり知りませんでした。
身近にあるものなのに実は色々わかっていない方も多いかもしれません。和菓子の由来には調べるほど奥深いものが多いのです。
今回は、そんな「ボーロ(ぼうろ)」について、歴史や由来等について調べてまとめてみました。また、おすすめの折箱についてもご紹介しますので、ぜひ最後までお読み頂ければ幸いです。
目次
「ボーロ(ぼうろ)」とは

「ボーロ」とは、主に「小麦粉に砂糖や卵などを加えて丸く成形し、焼き上げた焼き菓子の和菓子」です。
現在では、小麦粉の代わりにそば粉や片栗粉を使ったり、膨らましの為にソーダや重曹を混ぜたりとさまざまなバリエーションがあります。
形は、丸くて平たい形が多いですが梅花型もあります。種類により直径10センチほどのものから、指先ほどの大きさのものがあります。
「ボーロ(ぼうろ)」の歴史
南蛮菓子として伝来したボーロ

ボーロは、戦国時代、ポルトガルの宣教師や貿易商人より「南蛮菓子」の1つとして、日本へ持ち込まれました。
カステラや金平糖などもこの時期に日本へ持ち込まれたお菓子です。
参考:「カステラ」の由来とお薦めのテイクアウト容器
船員の保存食だったボーロ
当時のボーロは船員の長い航海の保存食でもあり、固くて小さなもので、クッキーに近いものだったそうです。固めのパンや麺類に使われる強力粉(硬質小麦)を材料としていました。
「ボーロ」の名前の由来
「ボーロ」という名前の由来は、ポルトガル語の bolo(ボーロ) にあります。これはもともと「菓子」全般を意味する言葉でした。
日本へ伝わった際にも、菓子の総称として使われていましたが、日本では現在に至る間に、みなさんがご存知のお菓子「ボーロ」のみをボーロと呼ぶようになりました。
日本での「ボーロ」の製法と進化
ボーロの製法は、長崎の出島のオランダ人より伝えられていきました。
江戸時代を代表する菓子製法の書「古今名物御前菓子秘伝抄」(1718)によりますと、「小麦粉と砂糖を使った焼き菓子で、上火を用いて作る」との記載があります。
当時砂糖は貴重であり、卵も宗教上食されなかった為、日本に合った改良が加えられ、日本独自の和菓子へと進化するのです。
和菓子用に薄力粉(軟質小麦)が使われ、サクッとふんわり感が出るものが作られるようになりました。
ボーロの種類

ボーロは日本各地で発展し、色々な種類がありますが、主に3種類に分けられます。
有名なのは、佐賀の丸ぼうろ、京都の蕎麦ぼうろ、関東で言えば「たまごボーロ」です。
丸ぼうろ
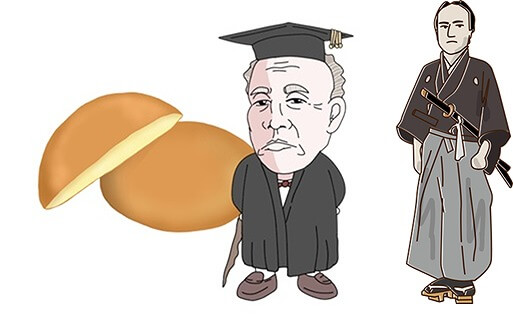
江戸時代の佐賀藩は、幕府より長崎警護の役目を受けており、地理的に西洋文化をいち早く取り入れる事が出来ました。
そのような背景のもとで誕生したのが「丸ぼうろ」です。
現在は佐賀県佐賀市や九州方面の代表的銘菓として親しまれ、「丸芳露(まるぼうろ)」、「丸房露(まるぼうろ)」という名前で販売されております。
大きさは約8センチで、中央が膨らんでいる丸い形です。
寛文年間(1661年~1672年)に、長崎在住のオランダ人から、佐賀藩御用菓子司の横尾市郎右衛門(いちろうえもん)が小麦粉と琉球糖を練り合わせ、天火で焼く製法を習ったことがはじまりと言われています。
その製法を継承したのが現在も続く老舗(元禄9年(1696年)創業)の「丸芳露本舗 北島」です。
また、1639年創業の老舗鶴屋の「丸房露」。天和年間(1681~1684)に2代目太兵衛が長崎でオランダ人から製法を取得し、丸房露をつくりはじめたとあります。
鶴屋では嘘のような本当の話があります。
佐賀出身で明治の元勲(げんくん)・大隈重信候が鶴屋に立ち寄った時の話です。
「茶菓として出された『丸房露』を食べた大隈侯は、「ほかに比類少なき風味」と感嘆し、東京に戻ってからもその味を懐かしんだそうです。
あまりに食べたくてたまらず、東京の自邸に鶴屋の第11代当主の善吉と職人を呼び寄せ、邸内に竈を築いて『丸房露』を作らせた」そうです。
早稲田大学の創設者でもあり、また、メロンも大好きだった大隈侯。
これらのエピソードにちなんで、早稲田大学の傍のカフェでは、丸ぼうろにメロンクリームを挟んだスィーツが販売されているそうです。
蕎麦(そば)ぼうろ

「蕎麦(そば)ぼうろ」は、京都銘菓のひとつで、小麦粉・砂糖・卵を使った基本の生地に蕎麦粉を加えて練ったものです。
中心に丸い穴を開け、梅花型に焼いています。そのヘルシーな特徴から健康志向の人々にも注目されています。
明治の末、京都の老舗蕎麦屋「河道屋(かわみちや)」が、蕎麦粉をぼうろに加えて梅型に焼いて売り出したのが始まりだそうです。
(「蕎麦ほうる」として登録商標されていて、ほうるはPole(蘭)Bolo(葡)の訛れるものという意味が込められています)。
以後、他店にも引き継がれていき、「蕎麦ぼうろ」が京名物になったそうです。
たまごボーロ

「たまごボーロ」は、小さくて可愛い球状タイプのぼうろの総称です。
繊細な歯ざわりとナチュラルな口溶け食感は、離乳期の赤ちゃんでも食べられる安心なお菓子として知られています。
赤ちゃん用のたまごボーロは生後7か月位が目安だそうですが、我が家では末っ子が食べている間、上の子達も隠れてつまみ食いしていたのを覚えています。
関東の方では「ぼうろ」というと、この「たまごボーロ」をイメージする方が多いと思います。我が家もそうでした。
しかし、実はこの呼び方は名古屋より北の地域に多く見られるもので、地域によって呼び名はさまざまです。
京都では「エイセイ(衛生)ボーロ」、大阪では「乳(ちち)ぼーろ」、九州では「栄養ボーロ」という呼び名で親しまれています。
そのルーツのひとつが、明治時代に誕生した「西村衛生ボーロ本舗」です。明治時代、疫病が大流行したことから子ども達に「栄養価が高く、衛生的で消化の良いお菓子を」との想いで「衛生ボーロ」を製造し始めた西村衛生ボーロ本舗の存在があります。
大阪の前田製菓の「乳(ちち)ぼーろ」は、北海道のばれいしょでん粉を材料に使っており、口溶けの良さにこだわっております。
それぞれのたまごボーロのネーミングには、その特徴や製造元の想いがあり、その地域ごとに根付いているのですね。
「ボーロ」にお薦めの折箱
コンビニ、スーパーも気軽に購入できる「ボーロ(ぼうろ)」ですが、観光地でのお土産やギフト用でも代表的な存在であります。
感謝の気持ちを包装にて彩るために、化粧箱として折箱を使って頂ければより高級感を演出できると思います。
紹介させて頂く商品は、こちらの折箱です。
本体 外寸 255×175×49mm(内寸245×165×41mm)と、かなり大きめな折箱です。
原反柄の杉柄も、和菓子にしっくりくると思います。
売り切り商品の為、箱1個の単価が50%オフになっており、10個入りでの販売。
ちょっとしたイベント用、行事用にも対応できるかと思います。いつもとは違う特別感を演出するのに最適なアイテムになるかもしれませんね。
他の和菓子との詰め合わせセットもいいかもしれませんね。
なお、商品カテゴリーにて「和菓子の折箱」を設けております。こちらも参照していただければ幸いです。
「ボーロ(ぼうろ)」の由来とおすすめのテイクアウト容器のご紹介、まとめ

ここまで「ボーロ(ぼうろ)」の由来、歴史や特徴、おすすめのテイクアウト容器の折箱についてまとめてみました。
戦国時代、宣教師や貿易商人より持ち込まれた南蛮菓子であるボーロ(bolo)は400年以上もの長い時を得て、赤ちゃんからお年寄りまで頂いている日本の和菓子、ぼうろとして親しまれております。
最近のボーロはカルシウムや乳酸菌、青汁入りなどの健康食品として、また、動物やキャラクターモノを印刷したものも数多く販売されております。
例えば福島県ですと、観光地のお土産として赤べこが印刷されたボーロが販売されています。その地域で親しまれるボーロを色々調べてみると面白いと思いますよ。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。この記事が少しでもお役に立てれば幸いです!
折箱は、お弁当をより魅力的に彩る容器です。ぜひ、あなたに最適なテイクアウト容器やお弁当容器を見つけてください♪
折箱堂では、安くて質の良い折箱を通販で購入することができます。ぜひお気軽にご利用ください。
折箱堂の商品一覧はこちら。





